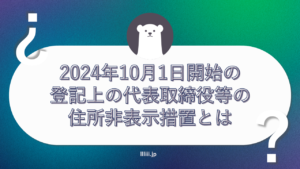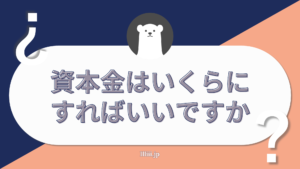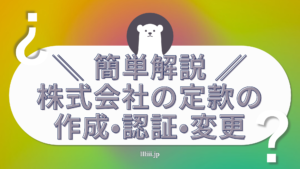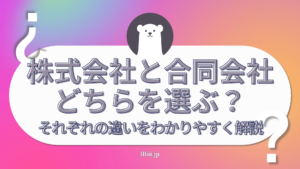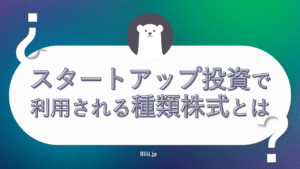香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
スタートアップ企業のよくある失敗のひとつに、複数人が共同で起業したときの特有の問題について十分な備えがされていないというのがあります。
具体的には、創業者間の持株比率の設定の失敗、創業者の誰かが離脱する際の取り決め(創業株主間契約)がされていない、取締役の任期の設定の失敗などがあります。
これらの問題に対する備えが不十分なまま共同起業した場合の失敗は、1人で起業した場合よりもダメージが大きくなる可能性は高いです。
今回は友人や仲間と、あるいはまったくのビジネス上の関係でもかまいませんが、共同で株式会社を設立するときの注意点についてとりあげます。
持株比率と議決権

私は、起業しようとしています。



よく見たら世の中を変える者の目をしていますね。



友人Aと50万円ずつ出し合って、株式会社をつくろうという腹づもりです。



いきなり、いちばんやってはいけないやつ。



え!やってはいけないことはやりたくありません。
どういうことですか。



株式会社に出資した人には株式が与えられます。
株式を持っている人が株主です。



私とAが株主になります。
そこは理解しています。



株主の権利のひとつに「株主総会で議決権を行使することができる権利」があります。



念のため、株主の権利をまとめると次のとおりです。
- 利益の配当を受ける権利
- 残余財産の分配を受ける権利
- 株主総会で議決権を行使することができる権利
- 株式を自由に譲渡することができる権利



わかったと思う。



議決権というのは、いいかえれば、会社の意思決定をする権利です。
1株いくらでもかまいませんが、1株1議決権という前提で考えてみてください。



2人で50万円ずつという同額の出資だと、2人の議決権が同じ数になりますね…



そうすると、2人の意見が割れたときに何も決められない膠着状態、いわゆるデッドロックになります。



では意見が割れたときにどちらの意見を優先させるか、あらかじめ決めておいて、出資額も考え直さないといけないということですね。



はい。創業メンバー全員を代表取締役にしている会社を見かけたりしますが、それもやめたほうがいいですね。
代表者はひとりにした方がいいです。



代表者の責任は重く、それに見合った株式を持つのが公平であるともいえます。
できるだけ代表者に株式を集中させておくことをおすすめします。
いくら友人相手でも上下関係ははっきりと決めておいたほうがいいですよ。



そうかもしれない。
代表者をひとりにして、代表者が株式を多く持つようにします。
株主総会の決議



創業メンバーの持株数に差をつけるというのは理解しましたが、どれくらいの差をつければいいでしょうか。



絶対的な答えはありません。
ただし、株主総会には普通決議と特別決議があります。それが参考になると思います。
普通決議(原則)
定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う
特別決議(原則)
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う



要するに、普通決議は議決権の「過半数」、特別決議は議決権の「3分の2」持っていれば決議できるという理解でかまいません。
ほかに「特殊決議」というものがありますが、レアだし、ここではとりあげません。



はい。



そして、普通決議と特別決議のそれぞれの決議できることは決められています。



おおまかにいって次のとおりです。
普通決議
- 取締役・監査役の選任
- 取締役の解任
- 役員報酬
- 剰余金の配当
特別決議
- 監査役の解任
- 募集株式の募集事項の決定(増資)
- 資本金の額の減少(減資)
- 株式の併合
- 定款の変更
- 解散
- 事業譲渡の承認
- 組織変更・組織再編(合併・会社分割など)



会社のかたちを変えることや株主の利害に重要な影響をおよぼす可能性のある行為は特別決議が必要です。



つまり議決権の3分の2を持っていれば、かなり重要な決定も1人でできるということですね。



そうですね。
しかし、さきほども言ったように代表者に株式を集めることをおすすめはしますが、会社が将来、投資家から出資を受ける可能性があるかとか、創業メンバーのモチベーションのことを考えたりしなければならず、絶対にこうしたほうがいいという答えはありません。



頭が痛いです。
でもここでメンバーの意見が一致しないと、この先難しそうですね。
創業株主間契約



創業メンバーが抜けるときにトラブルになるって聞きました。



はい。
もちろん創業メンバー全員が力を発揮して成功していくのが理想ですが、仲違いすることもありますし、やむを得ない理由で会社を離れなければならないこともあります。



あまり考えたくないですが。



で、問題になるのが、離脱するメンバーが持っている株式です。
これ、離脱メンバーが株式を譲ってもらえないとなると解決はかなり難しいです。
仲違いして辞めたメンバーが株式を持ったまま、ライバル会社に行くことだってありえます。
最悪の場合、会社を一からやり直すということにもなりかねません。



絶対にいやです。
どうすればいいですか。



創業時にあらかじめ、メンバーが離脱する場合には残る経営者に株式を譲渡する内容の取り決めをしておいた方がよいでしょう。
この取り決めを「創業株主間契約」といったりします。



創業株主間契約。
きちんと契約しておいたほうが良さそうですね。



そうですね。
万が一に備える保険と思って、取り決めをしておくことをおすすめします。
取締役の任期



他に気をつける点はありますか?



取締役の任期ですね。
取締役の任期は会社法の原則は2年ですが、株式の譲渡制限がついているいわゆる非公開会社は、任期を10年まで伸ばすことができます。



わかったと思う。



任期が2年だと、たとえ同一人物が再任され続けるとしても、任期ごとに役員の登記をしなければならず、コストがかかります。



任期10年にしておくと10年ごとに登記すればよくなるってことですね。
コストや手間が削減できていいと思いますが。



うまくいっているときはそれでもいいですけどね。
意気投合していっしょに事業をはじめたものの、メンバーが思ったよりもパフォーマンスを発揮してくれないな、とか思い始めるというのはよくある話です。



「メンバーが思ったよりもパフォーマンスを発揮してくれない」
・・・一生言われたくない言葉です。



それでいっしょにやっていくの無理だな、という段階までいったときに、自分から辞めてくれればいいですけど、辞めてくれないときどうするか、です。



さっき株主総会の普通決議で取締役を解任できるとありましたよね。
議決権の過半数があれば解任できるんじゃないですか?



実は解任はそう簡単にできることではないんです。
解任について「正当な理由」がなければ、解任された取締役は、会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。



「正当な理由」がなくても解任はできるけど、「正当な理由」がなければ、損害賠償請求されるかもしれないと・・・
「正当な理由」って具体的にどういう場合ですか?



経営能力が不足しているとか、経営方針が合わないぐらいでは正当な理由とはいえないとされています。
たとえば、会社の金を横領したぐらいのことが起きれば、正当な理由が認められる可能性は高いです。



法にふれてるじゃないですか。
犯罪レベルの話なんですね。
たしかに解任は難しそうですね。



はい。
それに解任した場合は、会社の登記簿の解任された取締役の欄にはっきりと「解任」の文字が刻まれることになりますので、解任の事実が公のものとなります。
これは会社の社会的な信用を大きく損なうおそれのある重大な問題です。



やば。



それに解任された取締役の今後の就職などにも悪影響を与える可能性があります。



そうかもしれない。



取締役の任期の話に戻りますが、結論、任期は会社法の原則どおり2年としておくか、あるいは短くして1年でもいいかもしれません。
短い期間で取締役の成績をチェックしていき、成績が思わしくなければ、任期満了時に「再任しない」ことで、退任してもらうことができます。
そうすれば損害賠償リスクも抑えられますし、対外的にも任期満了で退任してもらったという説明をすることができます。



最悪の場合に備えて、コストはかかっても任期は短くしておいたほうがいいのかもしれない。



それから、取締役は株式を持っている場合も多いので、さきほどの創業株主間契約とあわせて最悪のケースに備えておいたほうがいいでしょう。



事業をはじめるっていろいろ大変ですね。



うまくいくといいと思う。
でもできるだけ注意深くなった方がいい。
まとめ
- 創業者間で持株数を同数にすることは避けましょう
- 株主総会では普通決議と特別決議があり、それぞれ決議できることが決められています
- 株式を持っている創業メンバーが辞めたときに備えて創業株主間契約を締結しておきましょう
- 役員の任期は短くしておいたほうがよいでしょう
参考書籍
『ベンチャー企業の法務AtoZ』後藤勝也・林賢治・雨宮美季・増渕勇一郎・池田宣大・長尾卓(編集)|中央経済社
友人と共同で合同会社を設立する場合


当事務所のご案内


— どうぞお気軽にご相談ください。—