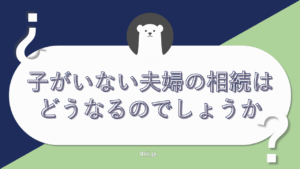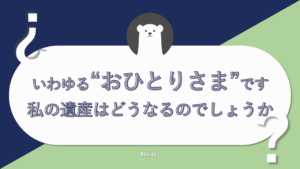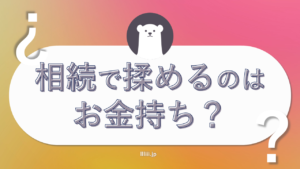香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
認知症になった人が有効な遺言書を作成することができるでしょうか。
結論としては、ほぼ手遅れの状態だといえます。
遺言のみならず法律行為は、意思能力がある人が自分の意思でしたものでなければ、無効とされています。
認知症の人が絶対に遺言書を書けないわけではありませんが、一時、判断能力が回復しているときに医師の立会いが必要という条件がついたりします。
また、たとえ書いたとしても、遺言者の遺言能力をめぐって争いになることがあります。
遺言書は元気なうちに書いておくことをおすすめします。
この記事では遺言書の作成と判断能力、制限行為能力者と医師の立会い、遺言能力の有無の争いなどを取り上げます。
遺言書作成と判断能力

相続がもめそうなので、親には遺言書を書いてもらいたいと思っています。



それはきちんと備えておいた方が安心ですね。



でも親が認知症なんですよね。
こういう場合どうなんですか?
書いてもらっていいですか?



うーん、正直、難しいですね・・・



やはりそうなんですか。



意思能力がない人がした法律行為は無効とされています。
遺言書を書くことも法律行為ですから、無効とされる可能性はあります。



意思能力って何ですか?



簡単にいうと、自分がする契約などの法律行為の結果を判断することのできる精神能力のことですね。



じゃあ絶対に遺言書を書けないってことですか?



絶対に書けないわけではないですが・・・
制限行為能力者と医師の立会い



書けなくないんですか?



遺言は、人の最終意思を尊重する制度ですから、15歳以上であれば未成年でもすることができます。
成年被後見人や被保佐人、被補助人などの「制限行為能力者」の人も遺言をすることができます。



制限行為能力者?



未成年や判断能力が低下した人を保護する制度で、判断能力が十分とはいえない人たちについて、その人たちがした法律行為は取り消すことができるとされています。
行為能力とは、単独で、完全に法律行為を行うことができる能力のことです。



成年被後見人・被保佐人・被補助人というのは成年後見制度ってやつですね?



そうです。
認知症などによる判断能力の低下の度合いによって支援の内容が変わってきます。
後見がいちばん判断能力の低下の度合いが重いということになります。
被保佐人と被補助人は制限なく遺言をすることができます。



成年被後見人は制限があるんですか?



判断能力が一時回復したときに医師2人以上の立会いのもと遺言することができます。



では、認知症でも遺言書を書くことはできるということですね?



不可能ではないです。
遺言能力の有無の争い



遺言書は書けたとしても最終的にその内容が実現されなければ意味がありません。



たしかにそうですね・・・



遺言の内容に不満がある相続人がいた場合どうなりますか?



う。まさか?



遺言者の遺言書を書いたときの判断能力を争うということになりがちです。



いやですね。
それで争いになるとどうなりますか?



遺言能力の有無は、個々の事案ごとに判断するしかありません。



はい。



遺言の内容、遺言者の年齢、心身の状況や健康状態、日ごろの遺言についての意向や遺言者と遺言により財産を譲り受ける人との関係、前の遺言の有無など、遺言者の情況を総合的にみて、遺言の時点で遺言の内容を判断する能力があったかどうか判定されます。



わかります。



判断能力の低下の兆候が認められる高齢者の遺言について、医師の診断や公証人とのやり取り、遺言の内容が打ち合わせ済みであったことや、その後の治療経過などから、遺言当時に遺言能力があったと認められる判例もあれば、公証人が作成する公正証書遺言であっても遺言者の遺言能力が否定された判例もあります。



やはり遺言書を作成するのは元気なうちにしておくのが安心ということなんですね。
まとめ
- 意思能力がない人が書いた遺言書は無効です
- 未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者でも遺言することは可能です
- 結論としては元気なうちに遺言書を作成することをおすすめします
参考書籍
『認知症に備える』中澤まゆみ・村山澄江(著)|自由国民社
『遺言モデル文例と実務解説〔改訂版〕』満田忠彦・小圷眞史(編集)|青林書院
『新訂 設問解説 相続法と登記』幸良秋夫(著)|日本加除出版
関連ブログ


当事務所のご案内


— どうぞお気軽にご相談ください。—