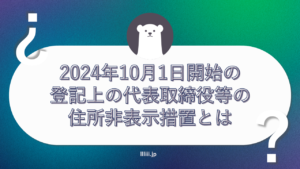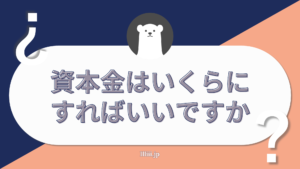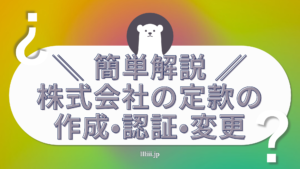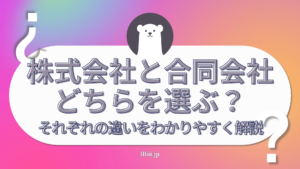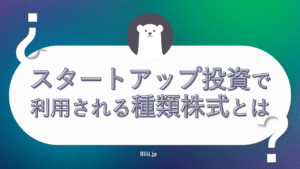香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
失敗を恐れるなとよく言われますが、失敗にはしていいものとしてはならないものがあります。
してはいけない失敗とは、あらかじめわかっていれば避けられたであろう失敗のことです。
単なる時間のムダに過ぎません。
しかし、やってしまう人は多いようです。
今回はスタートアップにありがちな創業期の資本政策について失敗事例を取り上げます。
資本政策そのものについては、こちらの記事をご参照ください。
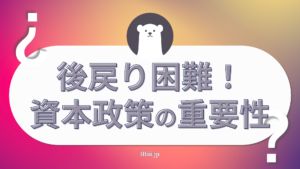
①創業者間の持株比率の設定ミス

友人Aと50万円ずつ出資して株式会社をつくります。



それってふたりの持株比率が50:50ということですよね。



そうです。



いきなりやってはいけないやつ。



やってはいけないことはやりたくありません。
どういうことですか?



持株比率が同じということは、株主総会での議決権も同じ数ということになります。
ふたりの意見が割れたときに何も決められない膠着状態、いわゆるデッドロックになります。



では意見が割れたときにどちらを優先させるか、あらかじめ決めておいて、出資額も考え直さないといけないということですね。



はい。
創業メンバー全員を代表取締役にしている会社を見かけたりしますが、それもやめたほうがいいですね。
代表者はひとりにした方がいいです。



そうなんですか。



代表者の責任は重く、それに見合った株式を持つのが公平であるともいえます。
できるだけ代表者に株式を集中させておくことをおすすめします。



代表者の責任は重いので、代表者に株式を集中させる。



韓国ドラマ「スタートアップ:夢の扉」で、主人公たちの会社の持株比率を決めるシーンがあります。
(Netflix 公式サイト)
https://www.netflix.com/jp/title/81290293



韓国ドラマ、観てるんですね。



メンバー間の仲が良くて、最初は持株比率を平等にしようとします。
ところが、メンターから今言ったような理由から代表者に株を集中させろというアドバイスをされた途端に、メンバーどうしがけんかをはじめるというシーンがあります。



私もドラマのように友人Aと熱いけんかをするかもしれない。
むしろ熱いけんかをしてみたいかもしれない。



いくら友人相手でも上下関係ははっきりと決めておいたほうがいいですよ。



考え直してみます。
②会社設立時の発行株式数が少なすぎる



持株比率を考え直してきました。
私が70万円、友人Aが30万円出資します。私が7割の株式を持ちます。



わかりました。どんな事業をするつもりですか?



Web5で世の中をいい感じにします。
上場したいです。



上場したいと思っている。
東証の鐘をいっしょに鳴らしたい仲間がいる。



1株1万円でいいでしょうか。
私が70株持って、友人Aが30株持つことになります。
わかりやすいですよね。



会社全体で100株ということですよね。
それだと1株を誰かに渡すと1%渡すことになってしまいます。



そうですね。
だめなんですか?



上場したいということでしたが、上場企業の株式1%持っているってすごいことなんですよ。



言われてみれば、そうかもしれない。



会社を設立した後に、投資家からの出資を受けたりストックオプションを発行するといった場面が登場します。
そこでは持株比率を1%以下の単位で考えなければなりません。
ところが株式数が少なすぎると、細かい単位での調整ができなくなります。
株式上場などの出口戦略ありきの会社設立であれば、設立時の発行株式数は多ければ多いほどいいです。



100株だと少なすぎるというわけですね。



設立時の株価なんていくらでもいいです。
株価を下げて株式数を増やしたほうがいいです。



わかりました。



この失敗は、まだ、株式分割という手続きでリカバリーすることは可能です。
ただし、時間と費用がかかるので、かなりもったいないです。
自分で会社設立の手続きをしている人はこういうミスをしている人が多いです。
はじめからわかっている専門家に相談して依頼したほうが、長期的にみれば安く済むことが多いと思いますね。
③創業株主間契約を結んでいない



ところで、友人と起業した場合、けんか別れすることもあると聞きました。



よくある話ですね。
あるいはやむを得ない事情で創業者のうちの一人が会社を去るということはあり得ます。
病気とか親の介護とか。



ありえますね。



いずれにせよ辞めた人が会社の株式を持ったままというのは、一気に経営が不安定になります。



友人Aが会社の株式30%を持ったまま会社を去ってしまったら困ります。
どうすればいいですか。



複数人で起業する場合は、創業株主間契約を結んでおくことをおすすめします。



創業株主間契約?



創業株主間契約というのは、創業者のうち、誰かがやめることになった場合に、誰がその辞めた人の株式を譲り受けるかあらかじめ決めておく契約のことをいいます。



なるほど。



もちろんチームとしてうまくいくのがいちばんいいですし、そうあってほしいです。
しかし万が一の保険として、あらかじめ契約しておくのがいいと思います。



そうですね。
うまくいかなかったときのことまで考えておきたいです。
④創業期に第三者に株式を渡しすぎている



実は、我々の事業に出資してもいいという人がいるのですが。



どんな人ですか?



地元の有名なお金配りおじさんです。



地元の有名なお金配りおじさん。



我々のようなスタートアップにとりあえずお金を出してくれる人がいるんです。
まじエンジェルって感じ。



いくら出してくれるんですか?



500万円です。
もらえるならほしいです。



地元で有名ってことは、まわりの起業家の人もその人から出資を受けていますか?



はい。
株式20%渡しているようです。



20%。
500万円の出資で20%。
株式を渡しすぎていますね。



そうなんですか。



ものごとには相場というものがあります。
数百万円の出資で20%は渡しすぎです。
将来、ベンチャーキャピタルから出資を受けるのが難しくなるかもしれません。



それは困ります。
私は上場を目指しています。



上場を目指しているのであれば、500万円の出資に対して渡せる株式は数パーセントに留めておくべきでしょうね。
10%でも渡しすぎるという印象です。
会社に外部資金を入れるかどうかは、株式を1%渡すのにも死ぬほど考えたほうがいいですよ。



そこまで考えていませんでした。



事業を加速させるためには外部資金を入れることが必要にはなってくると思います。
そのためには自分の持株比率を下げなければなりません。
その事業のスピードと持株比率の関係を考えて出資を受けるかどうか判断する必要があります。



そうですね。



また、出資者は会社の株主になります。
アドバイスをくれたり、人を紹介してくれたりと事業の成長に貢献してくれる人なのかどうか慎重に見極める必要があります。
そうでない人からの出資はプラスどころかマイナスにもなりかねません。



そうかもしれない。
株式を使ったファイナンスって難しいですね。
参考書籍
『起業のファイナンス増補改訂版』磯崎哲也(著)|日本実業出版社
『増補改訂版 起業のエクイティ・ファイナンス-スタートアップを成長させる「インセンティブ」の設計図』磯崎哲也(著)|ダイヤモンド社
当事務所のご案内


— どうぞお気軽にご相談ください。—