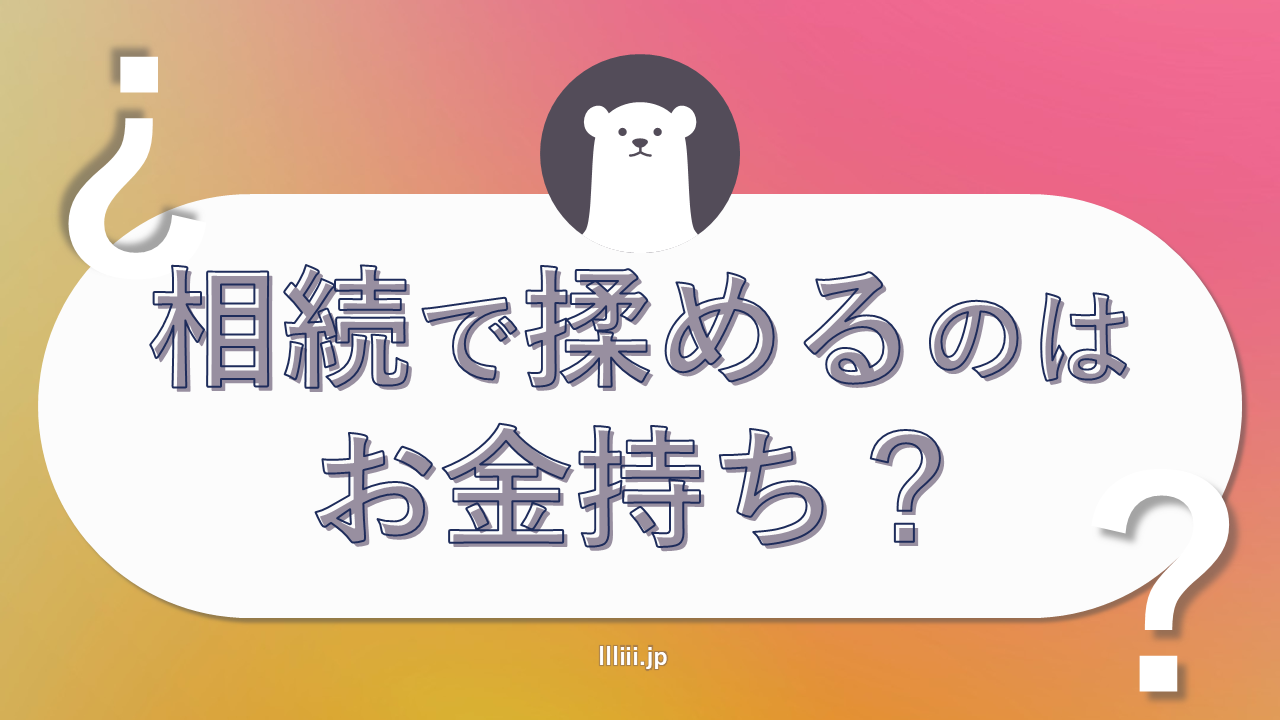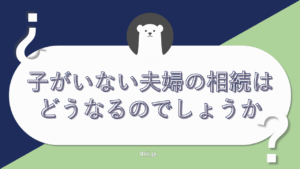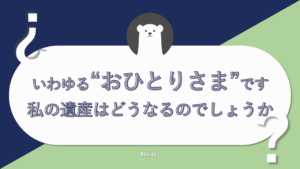香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
相続に関するよくある誤解のひとつに、「相続で争うのはお金持ち」というのがあります。
そのような誤解から、将来、相続トラブル・相続争いにつながることもあり得ます。
今回はどのような人が相続争いになりやすいか、相続争いの事例、相続対策について取り上げます。
どのような人が相続争いになりやすいか

映画「犬神家の一族」を観ました。
相続争いというのは恐ろしいものですね。



懐かしいもの観てますね。



やはり莫大な財産を遺すと争いが起きやすいんですね。
それに比べてうちの財産なんて自宅の土地と建物ぐらいのものだから心配いらないです。



実はそうとも限りません。
一般的な家庭でも相続争いは起こります。
「相続争いをするのはお金持ち」というイメージは、相続に関するよくある誤解のひとつです。



相続争いなんて犬神家のような家庭だけじゃないんですか。



裁判所の司法統計によれば、裁判所で調停など遺産分割事件になったものを、遺産総額別に事件数を分類した場合、5000万円以下が約75%を占めています。
遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(令和3年度)
| 遺産の総額 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 2310 | 33.0% |
| 1000万円超~5000万円以下 | 3052 | 43.6% |
| 5000万円超~1億円以下 | 866 | 12.4% |
| 1億円超~5億円以下 | 493 | 7.0% |
| 5億円超 | 28 | 0.4% |
| 算定不能・不詳 | 247 | 3.5% |
| 総数 | 6996 |



つまり相続争いが起こっているのはほとんど一般的な家庭ということになります。



司法統計の数字を出してきた。
なぜ一般的な家庭が争うんですか?



先ほど「うちの財産なんて自宅の土地と建物ぐらいのものだから心配いらない」とおっしゃっていましたが、そういう不動産のような分けにくい財産しかない場合は、揉めやすいです。



まさにうちが揉めやすいケース。



相続人が複数いれば、不動産を売って現金化しなければ分けられませんが、そもそも売りたくない相続人がいれば、揉めることになります。



なるほど。



仮に不動産を売って現金化することができたとしても、遺産の分け方に不満を抱いたり、過去の家族関係のしこりが影響して感情的な争いになってしまうこともあります。
相続争いの事例



たとえば、どういう事例がありますか?



では、実際にあったケースをご紹介しましょう。ある家庭では、ある男性が亡くなり、遺産として残されたのは自宅の土地と建物のみでした。相続人は、先妻との間の子Aさんと再婚した妻との間の子Bさんの2人です。
再婚した妻は先に亡くなっています。





Bさんは『母と住んでいた家だから、この家を引き継ぎたい』と主張しましたが、Aさんは『自分にも相続する権利がある。家の半分の価値を現金で支払ってほしい』と譲りませんでした。



確かに、家の価値をどう分けるかで揉めそうですね。



そうなんです。
Bさんは『母と一緒に住んでいた家を守りたい』と考え、Aさんは『正当な権利として取り分を求めるのは当然』と考えました。
双方が譲らず、話し合いが進まずに相続争いは長期化。
最終的に裁判にまで発展しました。



裁判ではどのように決着がついたんですか?



裁判所は、家をBさんが引き継ぐことを認める一方で、Aさんには家の評価額の半分に相当する現金を支払うよう命じました。
しかし、家の査定額に対する不満もあり、決着までに3年以上かかり、弁護士費用や裁判費用も大きな負担となりました。



そんなに長引くんですね。



相続争いというのは、第三者からみると、なぜそんな金額で揉めているのか理解できない、理屈を超えた感情的な世界だったりします。



甘く見ないほうがいいですね。
事前の相続対策



相続争いを防ぐためにはどうすればいいでしょうか?



先ほどの事例のように、先妻との間に子がいて、再婚して子がいるというようなケースは、遺言書を作成すべき典型例です。
このような典型例でなくても遺言書は作成しておいた方がいいですが。



遺言書を作成。



相続の基本的なルールとして、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をしなければならないというものがあります。
逆にいえば、遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を回避することができます。



どうやって遺言書を作成すればいいですか?



遺言者の一方的な思いだけで遺言書を作成しても、譲り受ける側が相続したいと思っているとは限らないので、相続人と話し合って遺言書を作成した方がよいでしょう。



先ほどの事例のように、相続人が複数で、めぼしい財産が自宅の土地・建物ぐらいしかない場合は、どうすればいいでしょうか?



生命保険を活用するという方法があります。
先ほどの事例で、裁判所が、Bさんが家を引き継ぐことを認め、Aさんには家の評価額の半分に相当する現金を支払うよう命じました。
そのような分割方法に備えて、Bさんを受取人とする生命保険を活用すれば、BさんからAさんへの家の評価額の半分に相当する現金の支払いを、保険金でまかなうということもできそうです。



生命保険の活用。
よくわかりました。
まとめると、まずは家族と話し合い、遺言書を作成する。
場合によっては生命保険なども活用してみるということですね。



そうですね。
早めの相続対策を講じることで、円満な相続を実現できます。
相続問題を未然に防ぐために、ぜひ適切な対策を検討してみてください。



参考になりました。
早速家族と話し合ってみます。
参考書籍
『新訂 設問解説 相続法と登記』幸良秋夫(著)|日本加除出版
『三訂版 相続登記の全実務 相続・遺贈と家事・非訟手続』田口真一郎・黒川龍(著)|清文社
当事務所のご案内


— どうぞお気軽にご相談ください。—