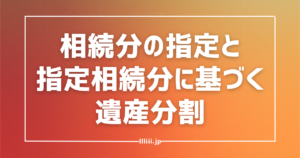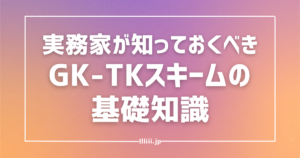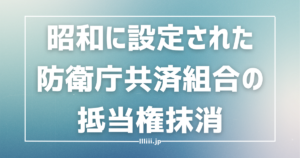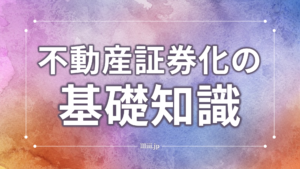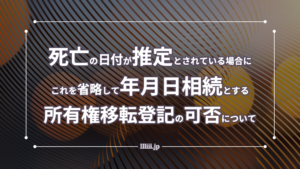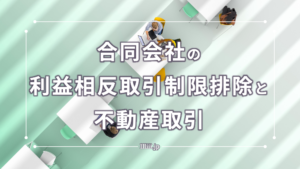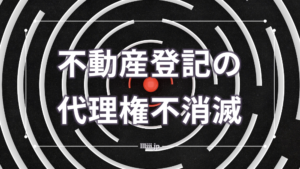香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
「根抵当権の債務者を個人A・Bから法人Cに変更するのは縮減変更にあたるのか」というタイトルをみて、縮減変更ではないでしょ?と思う人がほとんどなのではないかと想像しますが、どうでしょうか。
事例
個人事業主A・Bは家族で事業を営んでいます。
株式会社C(株主A100%出資、代表取締役A・取締役B)はA・Bの資産管理会社です。
A・BはD銀行から融資を受けて収益不動産として建物甲(A・B共有)を建てました。
建物甲にはD銀行を根抵当権者とする根抵当権が設定されており、その内容は以下のとおりです。
極度額 1億円
債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権
債務者 A B
(元本は確定していません。)
今回、A・B共有の建物甲の所有権を株式会社Cに移転する手続きをします。
典型的な利益相反取引にあたります、念のため。
資金の流れとしては、株式会社CがD銀行から融資を受け、売買代金をA・Bに支払い、A・BはD銀行に借入を全額返済するという実体上の手続きが行われます。
この元本確定前の根抵当権の取扱いはどうなるでしょうか?
D銀行は株式会社Cに融資をして、A・Bから返済を受けるため根抵当権者の地位は変わりません。
また、抵当権は特定の債権を担保するものですが、根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定されるものです。
このことから、既存の根抵当権を抹消して、再設定することなく、根抵当権の変更の手続きをすればよさそうです。
この場合、債務者の変更登記をします。
債務者
A・B → 株式会社C
A・Bの債務は借入全額返済により消滅しているため、債権の範囲の変更はありません。
これがもし、A・Bの債務を株式会社Cが免責的に引き受けるのであれば、債権の範囲の変更も必要となります。
ここで、本題の債務者A・Bを株式会社Cに変更するのは縮減変更にあたるかどうかですが、私は、あたらないと考え、根抵当権者を権利者、設定者を義務者で準備をして、当事者に案内をしていました。
ところが、D銀行担当者から、「本部にこれは縮減変更にあたる、ということで書類の準備をしていると言われたのですが、そうなんですか?」という内容の連絡がありました・・・
え?
債務者A・B→Aの場合の先例
ここで参考になるのは、債務者A・BからBが外れてAのみになるのであれば形式的に明らかな縮減変更となり、設定者有利、根抵当権者不利となるため根抵当権者が登記義務者となって申請する(質疑登研405P91)という先例です。
受験勉強でも出てきたので思い浮かぶ人も多いのではないでしょうか。
しかし、今回のケースでは、数だけみれば債務者が2名から1社になり減ることになりますが、設定者にとって有利とも不利ともいえない、と考えられるのですが・・・。
そこで、金融関連の実務に詳しい同業者に問い合わせてみたところ、同様のケースで根抵当権者を権利者として申請したら修正になったということでした。
法務局は単純に債務者の数しか見ていないと・・・。
自分が選んだ方法
実はそのとき管轄法務局に事前相談することができませんでした(その理由は省略します。)。
さて、どうするかということですが・・・
D銀行は、縮減変更だと思っているので、義務者としての書類が用意されます。
つまり、登記識別情報、登記原因証明情報(根抵当権変更契約証書)、委任状(援用型)が出てきます。
設定者(=債務者)側には、援用型委任状にサインしてもらいました。
これで、根抵当権者が権利者でも義務者でも、添付書類はどちらでもいけることになります。
もし、申請してダメだったとしても差し替えができるということです。
ということで、自分の考えのとおり、根抵当権者を権利者、設定者を義務者として申請しました。
すると、申請から3時間くらいで完了通知が来ました・・・。
結論としては、債務者の変更が「A・B→C」となる場合は交替的変更にあたり根抵当権者が登記権利者となるのが正しいはずですが、同様のケースの依頼がきたら、念のため管轄法務局に相談してみるのがいいと思います。
参考書籍
『不動産登記申請MEMO -権利登記編- 補訂新版』青山修(著)|新日本法規出版
— どうぞお気軽にご相談ください。—