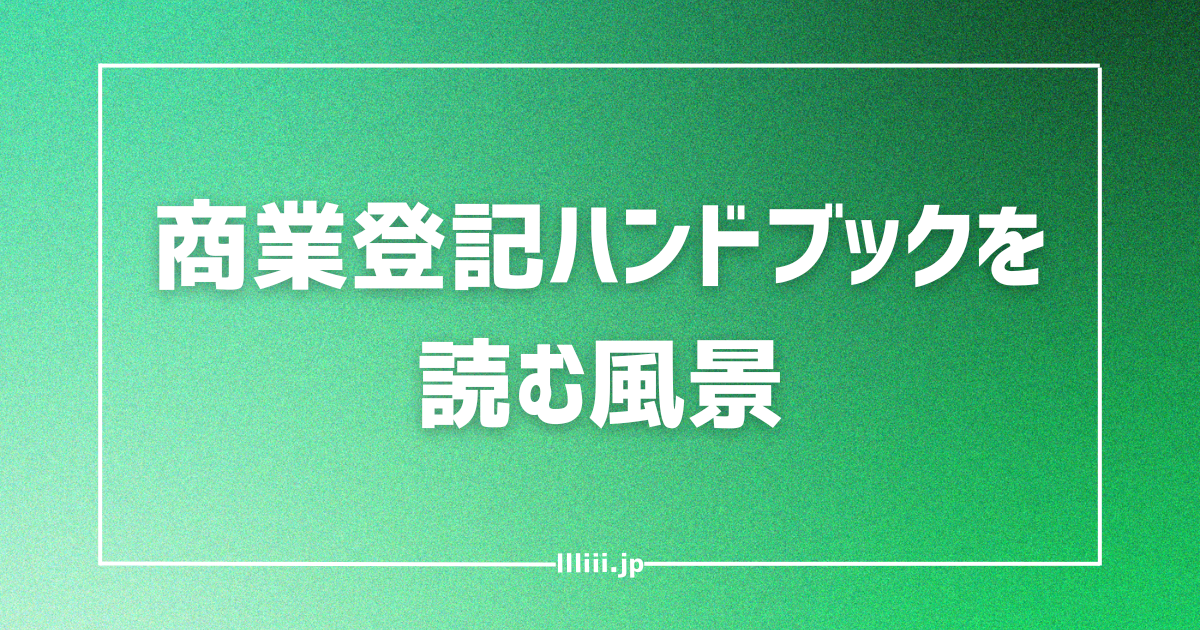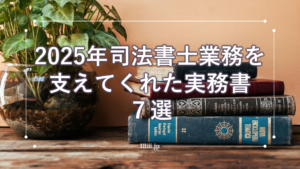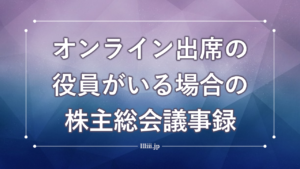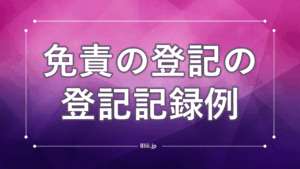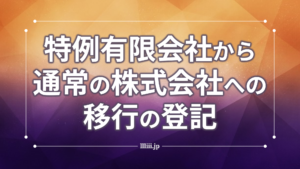香川県高松市の司法書士 川井事務所です。
この記事のタイトルをどうしようかと考えていた時のことだった。
書店で『吾輩も猫である』というタイトルの本を目にした時に、なぜか「商業登記ハンドブックハンドブック」というワードが天から舞い降りてきた。
商業登記の実務家にとってバイブルのような存在、それが「商業登記ハンドブック」。
そのハンドブックのハンドブック。
翌朝、冷静になってタイトルを見直してみた。
「生意気なタイトルだ」と思った。
これも手元に置いておけじゃないんだよ。
そこまでの内容は詰まっていないのである。
というわけで現在のタイトルに収まったのだった。
これは商業登記ハンドブック第5版を読みながら自分なり思ったこと、疑問点、恐れながら補足などを自分用にメモしたものでありながら公開してみるという試みです。
なので、繰り返し読むたびに加筆修正されていくかもしれません。 今回は「1-2②編」です。
1-2定款の記載例と留意点
引き続き商業登記ハンドブック(以下「ハンドブック」)を丁寧に読んでいく。
P.47~P.50取締役の員数等
C条関係
公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社除く)であれば、任期を10年まで伸長することができる。
株主・取締役1名の会社であればそれでよいかもしれない。
しかし、第三者と複数人で取締役を構成する場合は、原則どおり2年、あるいは1年を推奨している。
詳しくはこちらの記事に書きました。

P.50~P.51代表取締役
取締役会を置かない会社においては、代表取締役の選定方法の一つとして取締役の互選により定めるというのがある。
互選と聞いて思い出すのが、あなまちグループvs金子登志雄先生の以下のリンクの議論だ。
あなたのまちの司法書士事務所グループ|選任・選定・互選の意味~互選は過半数ではない
https://www.anamachigroup.com/%E4%BC%81%E6%A5%AD-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%90%91%E3%81%91/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%84%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98/%E9%81%B8%E4%BB%BB-%E9%81%B8%E5%AE%9A-%E4%BA%92%E9%81%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3-%E4%BA%92%E9%81%B8%E3%81%AF%E9%81%8E%E5%8D%8A%E6%95%B0%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84/
私は互選は過半数で決するということでよいと考えている。
しかし、上記のような細かい議論は専門家でない一般人にはわかりにくい話かもしれないし、互選という言葉が日常で馴染みがあるものかというとそうでない気がする。
どうしても定款に互選規定を入れたい場合は、「前項の取締役の互選による決定は、取締役の過半数をもって決定する。」というような文言を入れてもよいかもしれない。
なお、自分が関与する会社設立の場合、よほどのことがなければ、定款に互選規定を置くことはまずないと思う。
P.53~P.58取締役の責任免除及び責任制限
『平成27年施行改正会社法と商業登記の最新実務論点』48ページの「主張:責任免除等は定款で独立の章に」を読んでからというもの、定款上、独立の章を作って当該規定を置いている。
金子登志雄先生に感謝。
取締役会設置会社や理事会設置法人であれば設立時からこれらの規定を置くことはあると思う。
あと、設立時から上場などを目指すスタートアップであるとわかっていれば、設立時からいきなり責任制限の規定は置いているかもしれない。
P.65~P.72定款附則
A条関係
定款認証手数料が一律50000円の頃は「設立に際して出資される財産の最低額」を記載していたが、手数料の改正があってからは、「設立に際して出資される財産の価額」で記載するようになった。
認証手数料一律50000円は高いと思っていたが、今15000円に該当する定款の認証を公証人に依頼するときは、なぜか申し訳ないような気持ちになる。
B条関係
「なお、各発起人間において、払込みに係る金銭の額に応じて平等に設立時発行株式が割り当てられていなくとも、発起人の全員の同意により定めた以上、差し支えないとされている。」とあるが、税務上の問題がありそうなので、避けた方が無難だろう。
「設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額については、各発起人につき1円以上でなければならない(出資なくして株主となることはできない)が、各発起人10株単位で引き受けることを前提として、「10株につき1円」とすることは差し支えない。」とあるが、株式を発行して資金調達をしていく見込みのスタートアップであれば、あるいは試してみてもいいのかもしれない。
しかし、ほとんどの人がやっていないことをやると、

なんですかこれは?
と質問される可能性が高く、それに答えなくてはならない。
説明コストがかかることになるのだ。
E条関係
法人格のない組合や権利能力なき社団は株式会社の発起人になれないということが書かれている。
組合とは契約なのであって、法人格は有しておらず、法律上の権利義務の帰属主体とはなりえない。
一方、『論点解説商業登記法コンメンタール』P.152には、「発起人の資格には制限がないが、定款認証の際に印鑑証明書等が必要なことから、法人格のない民法上の組合が発起人となることは事実上困難である」という記載がある。
言い換えれば、印鑑証明書等の問題が解決されたら法人格のない民法上の組合であっても発起人になることができる、と読めるような気がしないでもない。
実体上組合等が発起人になれないことと、発起人の資格に制限がない(実体上組合等が発起人になれる)が手続上の理由により事実上困難というのでは、意味合いが違っている。
仮に後者(コンメンタール)が正しいということであれば、手続上の問題は解決されなければならないはず。
なお、投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)は法務局に印鑑を届け出ることになるため組合の印鑑証明書が存在する。
後者の立場によれば、LPSやLLPであれば発起人になれるということだろうか。
ハンドブックP.71の「ただし、募集設立の場合には、権利能力なき社団も株式の申込みをすることができ、株式申込者として、当該団体名のほか、その代表者等の氏名を記載するのが相当であるとされている(登記研究165号54頁)。」という記載については、会社成立後の株式会社が募集株式の発行をする際に、たとえば投資事業有限責任組合(LPS)が株式申込者となれることと同じ取扱いということだと考えられる。
つまり、ハンドブックでは「発起人」と「募集設立の場合の株式申込者や会社成立後の募集株式の発行における株式申込者」とでは求められる能力が異なると考えているように読める。
たしかに、会社法上、発起人の責任は、募集設立の場合の株式申込者と比べれば重いものとなっている(会社法第52条~第56条)。
ハンドブックの記載のとおり法人格のない組合や権利能力なき社団は株式会社の発起人になれないと思っておいた方がよい気がする。
ところで、そもそも権利義務の帰属主体とならない組合が株主になれるのか?ということについて疑問を持ちながら何年も月日が流れている。
このことについては単独で一記事になりそうなぐらい書くことがありそうだが、ずっと後回しにしている。
P.72~P.76現物出資等に関する定款附則
現物出資による設立はなくはないと思われる。
P.74「定款に記載する現物出資財産の価額は、厳密な時価ではなく、発起人が当該財産の価額として合意した価額である」という記載があるが、現物出資の場合は税務の問題が関わってくるので、税理士に相談するのが無難だろう。
関連記事
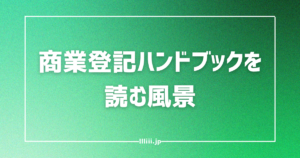
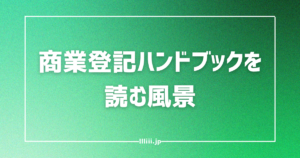
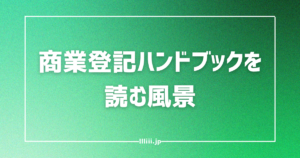
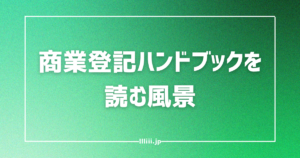
参考書籍
『商業登記ハンドブック〔第5版〕』松井信憲(著)|商事法務
『平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点』金子登志雄(著)・東京司法書士協同組合(編集)|中央経済社
『論点解説 商業登記法コンメンタール』神﨑満治郎・金子登志雄・鈴木龍介(編著)|きんざい
『論点解説新・会社法: 千問の道標』相澤哲(編集)|商事法務
当事務所のご案内


— どうぞお気軽にご相談ください。—